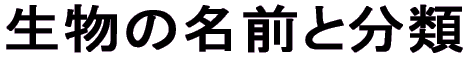 |
 |
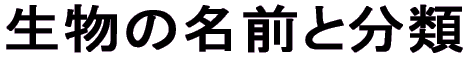 |
 |
生物の分類
種の概念
分類というのはまず生物に名前を付けるところから始まります。名前が与えられるのは種という集合体であり、人間の場合のように個体(個人)ごとに名前をつけることはありません(人間の種名は、ヒト Homo sapiens)。ところでこの種というのは定義の非常に難しい概念で、未だに万人が納得する定義がないというのが実状です。
古来より我々は形(形態)の違いでもって種を区別してきました。これが形態分類の原点です。例えば、イヌとネコ、モンシロチョウとアゲハチョウなど誰が見ても明らかに形態が異なるので別種とされるわけです。
ところで、イヌにはセントバーナード、ダックスフント、チワワなど様々な品種があり、例えて言えばニワトリとスズメくらいの形態的違いがあるのに、これらの品種は分類上は別種ではなく同一種で、学名はすべて Canis familiaris です。また、モンシロチョウの成虫と幼虫(青虫)は似ても似つかないほど形態的に異なりますが、これも同一種です。これらが同一種に分類される理由は、形態情報以外に品種改良の歴史や生活史の情報があるからです。ところが、形態以外の情報がない、または乏しい場合にはこれらが別種にされてもおかしくないかも知れません。
実際、同一種の成長段階や雌雄による形態の相違をとらえて別種として報告された例は数多く、例えばウナギの仔魚は葉型幼生と呼ばれて成魚とは全く異なる形態をしていますが、これが leptocephalus という学名の新種の生物とされたことがありました。その後それがウナギの幼体であることが判明しましたが、いまでも葉型幼生は leptocephalus(レプトケパルス)と呼ばれています(種名ではなく一般名として)。また山奥の清流に棲む体色の真っ白なイワメという淡水魚が新種記載されたことがありましたが、これはのちにイワナの白化個体(アルビノ)であることがわかりました。このような例は、現在有効な種とされているものの中にも十分にあり得ることが予想されます。
逆に、同一種と思われていたものが非常に微妙な形態的違いから種を分けられることもあります。テントウムシの一種にナミテントウというのがあって、これは従来1種とされていたのですが、成虫はそっくりなのに幼虫の形態が異なる2型があることがわかり、のちの研究でそれら2型は完全に生殖隔離をした別の集団であることが判明して、ナミテントウとクリサキテントウの2種に分けられました。
このように、形態的に微妙な差しかないのに完全に生殖隔離していて“生物学的種”と認められる関係は同胞種(sibling species)と呼ばれます。このような同胞種の事例は、近年生態学や遺伝学的研究技術が発展するにつれて特に多く見つかるようになり、ウスグロショウジョウバエ、ハマダラカ、ヒキガエルなどでよく知られています。魚介類でもこのような同胞種の例が最近特に多く報告されていて、スズキ、カワムツ、シマハゼ、ササノハベラ、メイタガレイ、ドブガイ、タイラギ、アカガイ、ナガウニ、マナマコ、ノコギリガザミなどで、従来一種とされていたものがいくつかの種に分けられたり分けられつつあります。
このように、形態的に違っていても同じ種であったり、逆に形態がそっくりでも別種であったりと、生物の種分類は非常に難しいと言えます。分類学は“分類が苦”なのです。しかしそのように混沌としたものの本質を解明していくのが分類学の醍醐味でもあります。
進化、種分化と分類
種は同じ遺伝資源を共有するので世代を経ても形態が変化しない普遍的な実体ですが、他方、地質学的な長い時間尺度から見ると種の形態はどんどん変化しているのです。例えば人類が、猿人→原人→旧人→新人と変化してきたように。これを生物の進化(evolution)といいます。
その説を唱えたのがイギリスの博物学者ダーウィン(Charles Robert Darwin, 1809–1882)であることは有名ですが、彼はガラパゴス諸島で島ごとに生物の種が異なることに気づき、それを他の島の集団と遺伝的交流が断たれた(自由に交配できなくなった)ために生じたものと考えました。このように生殖隔離によって新しい種が生じることを種分化(speciation, specific divergence)といいます。また種分化は、環境に適応した遺伝子を持つ個体だけが生き残ることによる自然淘汰や、あるいはひとつの種が時間の経過とともにあらたな種へと変わっていくことによっても起こります。こんにち我々が目にしている“種”というものはこのように長い時間を経て形成された進化のたまものなのです。
ところで、種分化はある日突然に起こるのではなく、数十万年~数百万年の時間の間に徐々に遺伝子と形態の変化が進行していくものと考えられます。といっても50億年以上と言われる地球の歴史の長さから見るとほんの一瞬の出来事かも知れませんが、しかし我々の時間尺度では相当に長い時間であると言えるでしょう。種分化というイベントは確率的に全くランダムに生じると考えられるので、いま現在でも種分化途中の状態にある生物も数多くあることが予想されます。前述の同胞種と呼ばれるものはその典型かも知れません。
ヨシノボリという淡水産ハゼには以前から数型の存在が知られていて、それぞれ生態的、遺伝的に明らかに相違するので、それらの型はすべて独立種ではないかと言われていました。しかし、いくつかの型は形態的に完全に識別することができないために、種分類の作業は足踏み状態となっています。おそらく、これらヨシノボリの数型は種分化がまだ完了せず、その途中段階にあるものと思われます。このヨシノボリの事例は、種分化の途中段階のものを分類上どう扱うのか、我々に与えられた試験なのかも知れません。
遙か昔に種分化が完了した種なら形態的に大きな違いがありますから形態分類は容易ですが、しかしそのようなわかりやすい材料はとっくの昔に分類が確定していて、いまの時代にはこのヨシノボリのような難しい材料しか残っていないのでしょう。このように、種分化の途中段階にあって別種になりつつあるものを、どの段階から種とするかの線引きをするのがこれからの分類学の残されたテーマになりそうです。
種分類から類型分類へ
種分類によってたくさんの種の存在が明らかになると、今度は形態的に似たものをまとめようという発想が生じます。これを、種分類に対して類型分類といいます。生物を形態の類似性によって分類するという思想は西洋では古くからあったようです。古代ギリシャの哲学者アリストテレス(Aristoteles,BC 384–322)は生物に関する著書を何冊も書いていて、その中で独自の動物分類体系を構築し、分類学の祖とも言える存在です。アリストテレスの分類体系は当時としては画期的なものでしたが、現在の体系に比べると極めて大まかで実際の系統とは異なる点も多くありました。アリストテレス以後もたくさんの生物学者が輩出して分類について考えましたが、17世紀までアリストテレスの体系からほとんど進歩がありませんでした。
1700年に、フランスの植物学者トゥルヌフォール(Joseph Pitton de Tournefort, 1656–1708)は植物を分類するのに形の似たものを集めて属(genus)という範疇を設け、種名の整理に大きく貢献しました。彼は、属の名をすべて1語のラテン語で表わし、その属に含まれる種は属名の後にその種の特徴を簡潔に表わす語(1語~数語)を付け加えて区別しました。ラテン語は古代ローマ帝国で使われていた言語で、トゥルヌフォールの時代には既に死語となっていましたが、当時のヨーロッパ世界では文語として文学や学術の世界で広く用いられていた国際言語でした。このトゥルヌフォールのやり方が現在における種の学名の形式の原型と言えるものです。
その後、スウェーデンの博物学者リンネ(Carolus Linnaeus, 1707–1778, 1761年に爵位を受けたのちは Carl von Linné と称される)は1735年に大著(Systema Naturae(自然の系統))の第1版を著し、その中で彼はトゥルヌフォールに倣って動物にも属という概念を導入し、さらに属の上の分類単位として目 (ordo)と綱 (classis)を設けました。目は類似した属の集合、綱は類似した目の集合ということになり、このような類型分けを階層分類といいます。ただ、このときの分類は今日のものに比べると相当に荒っぽいもので、“種(species)”が多数の種の集合に相当するものであったり、また現在の分類におけるいくつかの科をひとまとめにしたような分類群もありました。
その後リンネ式の階層分類はより細分化され、現在では次の表に示したようなたくさんの分類単位が設立されています。これを種分類に対して類型分類といいます。門 、綱 、目 、科 、属 、種 などの日本語は、明治時代に英語の専門用語が日本に入ってきたときに翻訳された新造語です。
分類体系の骨組みは門、綱、目、科、属、種であり、それに加えて例えば科グループの場合なら科の上に上科、下に亜科や族(属と混同しないように)の副次的な区分が必要に応じてなされることがあります。なお、分類用語には“種類”や“~類”という語はありません。これらは定義が極めて曖昧、あるいは意味が広すぎる一般語なので専門用語としては用いられないのです。
アサリ、カブトムシ、マダイについての分類学的位置を下に示しました。我々になじみ深い種でも分類学的にはしかるべき位置が決められているわけです。なお、マダイには南半球に生息するゴウシュウマダイという亜種があり(別種とされることもある)、学名はマダイの学名のあとに auratus という亜種小名がつきます。
動物界 Kingdom Animalia 軟体動物門 Phylum Mollusca 二枚貝(斧足)綱 Class Bivalvia ハマグリ(異歯)目 Order Heterodonta マルスダレガイ科 Family Veneridae アサリ属 Genus Ruditapes アサリ Ruditapes philippinarum
動物界 Kingdom Animalia 節足動物門 Phylum Arthropoda 昆虫綱 Class Insecta 甲虫(鞘翅)目 Order Coleoptera コガネムシ科 Family Scarabaeidae カブトムシ属 Genus Allomyrina カブトムシ Allomyrina dichotoma
動物界 Kingdom Animalia 脊椎動物門 Phylum Vertebrata 硬骨魚綱 Class Osteichthyes スズキ目 Order Perciformes タイ科 Family Sparidae マダイ属 Genus Pagrus マダイ Pagrus major
動物界の主要な門とそれを構成する生物について下の表にまとめました。我々になじみ深い生物以外にもさまざまな生き物がいることがわかります。ここに示した以外にもいくつかの門が提唱されていて、また、どの分類群に属するべきか研究者によって意見が分かれていてる生物もあります。
原生動物 Protozoa アメーバ、ホシズナなど 海綿動物 Polyfera カイメン 腔腸動物 Coelenterata クラゲ、イソギンチャク、サンゴ 有櫛動物 Ctenophora ウリクラゲ、フウセンクラゲ 扁形動物 Platyhelminthes ウズムシ(プラナリア)、ヒラムシ 曲形動物 Kamptozoa スズコケムシ 紐形動物 Nemertinea ヒモムシ 袋形動物 Aschelminthes ハリガネムシ 環形動物 Annelida ゴカイ、ミミズ、ヒル 節足動物 Arthropoda エビ、カニ、昆虫類など 軟体動物 Mollusca 巻貝、二枚貝、イカ、タコ 星口動物 Sipuncula ホシムシ 触手動物 Tentaculata コケムシ、シャミセンガイ 棘皮動物 Echinodermata ウミユリ、ウニ、ヒトデ、ナマコ 原索動物 Protochordata ホヤ、ナメクジウオ 有髭動物 Pogonophora ヒゲムシ 半索動物 Hemichordata ギボシムシ 毛顎動物 Chaetognatha ヤムシ 脊椎動物 Vertebrata 魚類、両生類、爬虫類、鳥類、哺乳類
リンネの二名法
前述のリンネの Systema Naturae はその後改訂を重ね、1758年には第10版が出版されるに至りました。その中では種の表記方法が統一され、ラテン語の1語の属名に1語の修飾語または同格の名詞を伴って表わされました(それ以前の版では修飾語に1語~数語が用いられていた)。これを二名式命名法(二名法)(nomenclator binominalis)といいます。現在の生物種の学名はすべてこの形式に従ったもので、この印刷物で初めて学名の形式が統一されたことになります。そこでこの印刷物の出版年月日を1758年1月1日とみなし、それを動物命名法の発祥の日とみなすことになりました。現在の国際動物命名規約ではこの日以後にこの形式によって命名された種名が有効な名称として使用されており、それ以前の名称は認めないことになりました。
国際動物命名規約
リンネ以降、分類学は発達し、1800年代になるとリンネの当時の何十倍もの数の種が記載されました。そのように夥しい数の種名が作られるようになると、同じ種が違う名前で何度も記載(発表)されたために生じる同物異名(synonym)や、逆に違う種に同じ名前が付けられる異物同名(homonym)が多くみられるようになってきました。そうなると甚だ不都合なことになりますから、名前の付け方について統一する必要が出てきました。そのような必然性の中から生まれたのが統一基準が国際動物命名規約です。この規約が権威のあるルールとして定着するまでには様々な紆余曲折がありましたが、各国の学者たちが何度も協議を重ね、1905年にその前身である萬国動物命名規約(International Rules of Zoological Nomenclature)が出版されました。その後1961年に内容を一新した国動物命名規約(International Code of Zoological Nomenclature)が出版され、以後改良を重ねて1999年にはその第4版が出版されています。
この国際動物命名規約では生物の命名法や学名の取り扱いについてこと細かく規定されていて、いわば分類学における憲法的な存在になっています。内容の概要についてはのちほど解説したいと思います。
現在では、動物、植物、園芸植物、菌類のそれぞれに独立した国際命名規約があり、細かい部分では相互にかなりの相違があって、特に植物の種名の表記はかなり煩雑になります。
日本における分類学の歴史
リンネの時代に西洋で博物学(分類学)が発展していたころ、日本は江戸時代でした。西洋と対照的に東洋では分類という発想はなぜか発達しなかったようで、日本でも生物学や分類学は明治の文明開化の時代に西洋から輸入されるまでほとんど発達しませんでした。
江戸時代までの生物学(博物学)に関する文献としては、魚類では四国の高松藩主の松平頼恭が江戸中期に編纂した「衆鱗図」、貝類では江戸末期の博物家である武蔵石寿(本名孫右衛門)が1843年(天保14)に出版した「目八譜」(目八は貝の字をばらしたもの)という図鑑的な書物があった程度でした。
江戸時代の日本は幕府の鎖国政策によって外国との交易がない状態が長く続きましたが、その中で例外として唯一交流があったのがオランダでした。オランダとの交易の窓口として唯一開港されていたのが長崎でしたが、ドイツ人でオランダ商館付属医師の命を受けたシーボルト(Philipp Franz von Siebold(日本ではオランダ語読みでシーボルトと称されるが、彼はドイツ人なのでドイツ語読みのジーボルトという発音が本来), 1796–1866)が1823年8月にに長崎の出島に赴任しました。彼は医師の仕事とともに日本についての調査研究の任務も帯びていたので、滞在期間中積極的に日本の動植物の標本収集を行ないました。
前述のように当時の日本には分類学や分類学者というものが存在せず、そこの動植物は西洋に知られていないものばかりでしたから、西洋の生物学者たちにとっては日本は新種の宝庫でした。シーボルトは採集した標本を乾燥(剥製)標本あるいはアルコール液浸標本(焼酎等の度数の高い酒を用いた)にしてオランダ本国に送り続けました。同時に、川原慶賀という日本人絵師に命じて生時の標本を詳細に描写させて美しい図版も作成させました。彼は6年半の日本滞在期間中に実に400種以上の日本産動植物の標本をオランダに送っています。
しかし、彼が送ろうとしたものの中に伊能忠敬による日本地図等の禁輸出品が含まれていたことが発覚したことから国外退去処分となり(いわゆるシーボルト事件)、1830年にオランダに帰国しました。
シーボルトの後任で長崎にやってきたのがビュルゲル(Heinrich Bürger, 1806?–1858)という人物で、シーボルトの仕事は彼に引き継がれました。彼はシーボルト以上に熱心に標本収集に励み、シーボルトが為したのをはるかに上回る1300種、総数2000点以上の標本を本国に送りました。しかし彼の標本はオランダへの途上で当時オランダ領だったジャワで長期間足止めされたことがあり、その際に相当数が失われた可能性があります。
シーボルトとビュルゲルによってオランダにもたらされた日本産動植物の標本はライデンにある国立自然史博物館の館長であったテンミンク(Coenraad Jacob Temminck, 1778–1858)に託され、脊椎動物担当のシュレーゲル(Hermann Schlegel, 1804–1884)や無脊椎動物担当のデ・ハーン(Wilhem de Haan, 1801–1855))らによって詳細に調べられました。
シーボルトは日本滞在中から日本の動物を記述した日本動物誌(Fauna Japonica)と植物を扱う日本植物誌(Flora Japonica)を刊行する構想を持っていて、帰国後それを実行に移しました。しかしシーボルト自身は生物学者ではなかったので、その仕事を全面的にテンミンクらに委ねたのです。日本動物誌「ファウナ・ヤポーニカ」は「甲殻類編」、「魚類編」、「爬虫類編」、「鳥類編」、「哺乳類編」の5巻から構成されていて、その中の「魚類編」ではアユ、マイワシ、キビナゴ、ウツボ、ウナギ、メダカ、タツノオトシゴ、ヒラメ、マダイ、マアジ、ブリ、トラフグ、カワハギなど日本人によく知られた魚がことごとく新種として記載されました。そのときに、川原慶賀の描いた多くの絵も活用されました。
「魚類編」の実質的な著者は国立自然史博物館スタッフのシュレーゲルと思われますが、公式には館長のテンミンクとの共著として扱われています。そのため、前述のような魚種の学名の命名者はすべて“Temminck and Schlegel”となっています。また「魚類編」の中でテンミンクに献名されたカワムツ Zacco temmincki の学名もあります。
「ファウナ・ヤポーニカ」の出版以降も、日本からもたらされた国立自然史博物館の収蔵標本は欧州のいろいろな研究者によって調べられ、研究に功績のあったテンミンクとシュレーゲルに献名して新種記載が行なわれました。テンミンクの場合は、ルリハタ Aulacocephalus temmincki、イトヒキベラ Cirrhilabrus temmincki、ウミタナゴ Ditrema temmincki、シュレーゲルの場合は、クロダイ Acanthopagrus schlegeli、クロソイ Sebastes schlegeli、アカカマス Sphyraena schlegeli、ヨウジウオ Syngnathus schlegeli などがあります。
しかし意外なことに、日本産の標本をヨーロッパにもたらした大きな功績者であるシーボルトに献名された学名は少なく、わずかにヒメダイ Pristipomoides sieboldi がある程度です。また、またシーボルト以上の功績者であるビュルゲルの場合は、ダイナンギンポ Dictyosoma burgeri、アオバダイ Glaucosoma burgeri、ナガサキトラザメ Halaelurus burgeri の程度で、やはり現代と同じように当時も学名というものは学者だけの世界のものだったのかも知れません。
このように、日本は分類学が発展しなかったために、日本産の主要な動植物の命名はほとんど19世紀の欧州の学者によって為されていて、おいしいところは全部外国に持って行かれたという感じです。
さて時代は下って明治になると、それまで禁止されていた西欧文明が怒濤のごとく日本に流入し、その影響からかようやく日本人の生物学者が現れるようになりました。植物では牧野富太郎や南方熊楠、魚類では田中茂穂など、日本におけるその分野の分類学のパイオニアが輩出し、現在の分類学の礎を築きました。しかし、土壌生物(ミミズ、ヤスデなど)やウミウシ類など、分類の専門家が未だに数少ない分類群ではまだまだ調査研究が十分に進んでおらず、今後の発展が期待されます。
生物の呼び名について
生物の呼び名は、同じ種であっても国や地域ごとに異なります。それを世界共通の統一名称にしたものが学名(scientific name)です。学名は、前述のようにリンネの Systema Naturae(第10版)がその発祥とみなされ、現在では国際命名規約によってその取り扱いが厳密に統制されています。また学名は種名だけを指すのではなく、前述の門、綱、目、科、属、種などの分類階級の名称も学名です。
日本のマスコミなどでは、ブラックバス(学名オオクチバス)、北寄貝(学名ウバガイ)、都鳥(学名ユリカモメ)などと表記されることがあり、一般にもこのように理解されているむきがあります。しかし、( )内の名称は学名ではなく標準和名であり、学名と混同されることがあるので注意が必要です。一般の人にほとんど縁のない生物の名前は学者の間だけで通用する学術名のような感があり、そのために標準和名が学名と勘違いされるのかも知れません。
和 名
和名の“和”とは、和服や和食の“和”であり、つまり日本のことを指します。生物の和名(Japanese name)というのは、日本におけるその種の呼び名ということになります。日本産の生物の大部分には和名が与えられていますが、細菌やプランクトン、あるいは外国産の生物の多くには和名がなく、学名のみで呼ばれるものもあります。また、恐竜などの化石種の種名もほとんどの場合学名で呼ばれます。
同じ種であっても日本も広いので地方によって呼び名が異なることがあります。それを統一するために用いられるのが標準和名(common Japanese name)で、これには専ら関東地方におけるその種の呼び名が用いられます。明治維新以後に日本語の標準語として関東方言が採用されたのと同じ理由です。近年に新種記載された種の場合には、それを記載した研究者(論文の著者)が標準和名をつけることになります。生物の和名は専らカタカナ表記により、生物学の範疇ではひらがなや漢字表記は用いられません。人の場合でも生物種としての表記は“ヒト”となります。
和名の取り扱いには学名の場合のような規則はなく、先取権の原則もありませんが、それに準ずる扱いが推奨されます。しかし、研究者による見解の相違や、分類体系が変更されるときに和名が変更されることも往々にしてあり、取り扱いはかなり寛容あるいは曖昧と言えるでしょう。
また古くからの慣習も強く残っており、例えば、標準和名シログチというニベ科の魚はイシモチという名前でもよく知られていて、双方の名称がほとんど遜色なく通用しています。また、北の地方でホッキガイという名前でよく知られたバカガイ科の二枚貝は標準和名をウバガイといいますが、少なくとも水産上はウバガイという名称は全く用いられず、どうもウバガイという“標準和名”は学者の世界だけのものとなっているようです。植物でもジャガイモとバレイショのようにふたつの和名が通用している例があります。
このような同物異名ばかりではなく異物同名のケースもあり、例えばホトトギスという生物が鳥類と二枚貝類の両方にあったり、ハゼやスギという生物が植物と魚類の両方にあったりします。
マスメディアなどでは、生物名の表記に際して標準和名が偏重される傾向があり、標準和名が唯一無二の“正式な名前”であるかのように扱われがちですが、前述のように実際にはかなり曖昧なものです。
私の個人的な意見として、地方における名称もそれなりに尊重して後世に残していくべきと思っています。例えば、標準和名キジハタというハタ科の魚は学名を Epinephelus akaara といって、前述のシーボルトが標本を母国のオランダに持ち帰り、長崎地方におけるその魚の名称であるアカアラをそのまま種小名に用いたものです。キジハタという標準和名は関東地方におけるこの魚の呼称ですが、一方この魚は瀬戸内海の地方では広くアコウまたはアコウメバルと称され、キジハタやアカアラなどの名称では全く通用しません。しかしこれら全ての名称はその地方における“正式名称”であって、標準和名以外の名称が“俗称”であるかのように扱われるべきではありません。
標準和名は共通性、普遍性という意味で重要ではありますが、それ以外の地方名称も決しておろそかにされてはなりません。前述のようにそもそも標準和名というのは関東地方における地方名称であり、それがたまたま東京が遷都されたために全国共通の名前として扱われるようになっただけなのですから。日本語の標準語にしても、関ヶ原の合戦でもし西軍が勝利していたとしたら、関西方言が標準語となっていたであろうように・・・
英 名
英語圏の国では、日本における和名と同様に生物につけられた英語の名前(英名)(English name)があります。イヌやネコのように汎世界的に生息する種には元来英名がありますが、日本固有の種には英名がありませんから外国産の近似種の英名を当てることになります。ところが多くの場合、単一種ではなく近似種の総称であったり、同じ種が国や地域によって違う名前で呼ばれていることも少なくありません。
例えば、淡水魚のブラックバスというの日本ではしばしば largemouth bass Micropterus salmoides のことを指しますが、実は英語の black bass というのは Micropterus 属魚類の総称であって、単一の種を指す用語ではありません。
ブリ Seriola quinqueradiata の英名としてよく yellow tail が用いられますが、オーストラリアではバラクーダ(オニカマス)が yellow tail とも呼ばれます。また最近ルアー釣りが盛んなスズキ Lateolabrax japonicus は sea bass としてよく知られていますが、東南アジアはアカメの一種 Lates calcarifer が sea bass と呼ばれ、さらに Lates calcarifer は Baramudi という英名でも有名です。
このように英名は一般に和名よりもさらに曖昧なことが多く、その英名がどの種を指しているのか特定するために学名を併記することが重要となります。
学名について
学名の言語
学名はラテン語で書かれます。ラテン語は、イタリア語、フランス語、ルーマニア語、スペイン語、ポルトガル語などラテン系諸言語(ロマンス語)の祖先語で、前述のようにトゥルヌフォールやリンネの時代の国際語でした。リンネの時代にはラテン語を使う民族は既に存在せず、どの国の学者にとっても中立であったということも学名にそれを用いることが支持された理由でしょう。
ラテン語の単語にはギリシャ語からの借用語が多く、そのために学名に用いられる語にもギリシャ語由来のものが多くあります。ラテン語とギリシャ語は同じインド・ヨーロッパ語族に属するものの、言語学的にはかなり系統の異なる言語です。しかし、古代ギリシャが地中海沿岸地方で最も早くから文明が開け、その近隣の地方に文化的に大きな影響をおよぼしていたために、ギリシャより遅れて発展したローマ帝国の公用語であったラテン語にもギリシャ語の影響が多々みられます。これは、古代の東アジアで古くから文明開化していた中国の文字である漢字が朝鮮半島や日本など後進の近隣地域にどんどん広まっていったのによく似ています。ギリシャ語の単語はギリシャ文字を一定の規則に従ってラテン文字に置き換えるとラテン語化され、読み方は後述するラテン語の読み方に従います。
ラテン語のアルファベットは後述するように英語のアルファベットからWを除いた25文字ですが、学名では外国語の表記のためにWの使用も可能なので結局英語の26文字と同じです。漢字、ハングル、アラビア文字、キリル文字などによって綴られたものは学名とは認められませんが、発音をラテン語のアルファベットで表わせばラテン語化されたものと見なされ、学名とできます(例:“日本”は不可→“nippon”は可)。
欧米諸言語にはラテン語にない記号付きの特殊文字が含まれることがありますが、それらを含む語を学名に用いるためにラテン語化するには原則として記号を取り除きます。即ち、フランス語の é、è、ê は e、スペイン語などの ñ は n、北欧語の ø は o、å は a となります。ただし例外として、ドイツ語のウムラウト記号を伴う母音については、ウムラウトを母音から取り払い、その後に“e”を挿入します(例:Günther(ギュンター)という魚類学者に献名された学名は guentheri(ギュンテリ)となる)。
学名の読み方
国際命名規約では学名の読み方までの規定はありませんが、前述のように学名は基本的にラテン語で書かれていますから当然ラテン語の読み方に従って発音すべきです。ラテン語の発音体系は基本的にいわゆるローマ字式の読み方によります。ですから例えばコイの学名 Cyprinus carpio を“サイプリナス カーピオ”などと英語式に読んではなりません(正しくは キュプリヌス カルピオ)。そこでまずラテン語の文字と発音について以下に解説します。
文 字
ラテン語のアルファベットは下の表に示す25文字で、ほとんど英語と同じで(Wだけがない)ドイツ語やフランス語にあるような特殊文字はありません。このうち Y と Z は1世紀頃のギリシャ語からの借用語で、K も専ら外国語の表記に用いられます。
大文字 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z 小文字 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v x y z 文字の名称 アー ベー ケー デー エー エフ ゲー ハー イー イェー カー エル エム エヌ オー ペー クー エール エス テー ウー ウー イクス ユー ゼータ
母 音
ラテン語の母音はa、e、i、o、u、y の6種類あり、前の5個の発音はそれぞれ日本語のア、エ、イ、オ、ウとほぼ同じです。y も母音で、ドイツ語の ü あるいはフランス語の u と同じように発音します。この発音は仮名表記が難しいのですが、日本語ではイとユの中間のような音になります。前述のコイの学名にも含まれていますが、ここではユと表記することにします。ちなみに、日本語のヤ行の半母音(英語の y)はラテン語では j または i で表音します。
母音は単独の場合はそのまま発音し、英語のように a をエイ[ei]、i や y をアイ[ai]などと発音してはなりません。重母音はラテン語の場合、ae、au、oe、ei、eu、ui の6種類がありますが、ei、eu、ui は希で、偶然の母音連結やギリシャ語から来た単語などにみられます。ae、au、oe の場合は後の音を弱めに発音して、それぞれアェ(アィ)、アゥ、オェ(オィ)のような感じになります。ei、eu、ui の場合は重母音ではなく別々の母音として発音しますから、それぞれエイ、エウ、ウイとなります。
つまり、ラテン語の母音をカタカナ表記する場合にはそのままローマ字式に読んで実用上は大きな支障はないということになります。特に、ae をエー、au をオー、eu をユーなどと英語式に読まないように注意が必要です。また、ar、er、ir、or、ur を英語式に発音(カタカナ表記では長音)してはなりません。母音+r の発音です。
子 音
ラテン語の子音の多くは発音が英語の場合とほとんど同じですが、特に発音に注意すべきものについて以下に解説します。
c は、後に来る母音に関わらず常に[k]の音になります。例えば ci はキ(英語、フランス語のようにシ、イタリア語のようにチとはならない)、ce はケ(英語、フランス語のようにセ、イタリア語のようにチェとはならない)となります。
そもそも、後に来る母音によって子音の音が変わるという現在の発音規則は特殊化たものであり、子音の音はひとつに固定されているのが本来です。
例:Cicero(キケロー)、centrum(ケントゥルム)、species(スペキエース)
j と v は半母音で、それぞれ[y]と[w]の音を表わします。英語式の読み方をしないように特に注意が必要です。なお、古いラテン語では j と v の代わりに i と u がそれぞれ用いられていて、例えば major を maior と綴っても間違いではありません。
例:japonicus(ヤポーニクス)、Julius(ユーリウス)、vagina(ワーギナ)、Venus(ウェヌス)、virus(ウィールス)
x と z は複子音(ふたつの音を持つ子音)で、それぞれ[ks]、[dz]の発音になります。特に x の発音に注意が必要で、英語式に濁ったり[kis]と発音せずに常に[ks]です。z の場合は日本語のザ行の発音でほぼ差し支えありません。
例:examinator(エクサーミナートル)、xenon(クセノーン(キセノン、ゼノンと発音しない))
同じ子音が重なる場合は別々にふたつの子音として発音します。現代の欧米諸言語のようにひとつの音にならないので注意します。
例:attitudo(アッティトゥードー)、baccar(バク(ッ)カル)、communius(コムムーニウス)、cassis(カス(ッ)シス)、Mallius(マルリウス)、Tennes(テンネース)
bs は[ps]、bt は[pt]の発音にそれぞれ変わります。
ch、ph、rh、th は古典ギリシャ語のχ、φ、ρ、θをそれぞれ書き換えたもので、本来ラテン語にはない音です。古典ギリシャ語のχ、φ、ρ、θは帯気音(有気音)と呼ばれ、韓国語や中国語にある喉の奥からの無声の呼気を伴う音です。これらの発音を仮名表記することは難しいので、実用的には h がないのと同様に発音、表記してよいでしょう。古典ラテン語ではこれら帯気音の発音は特に強く意識されていたようですが、後世になると h がないのと同様に発音されるようになりました。
なお、ph はローマ時代の後代になって f の音に変化し、その発音は現代フランス語、英語に引き継がれています。つまり、ph を f の音で発音してもラテン語の発音として間違いとは言えないのですが、やはりギリシャ語を表音したときの元々の発音に従うべきでしょう。
特に ch は、現代の欧米諸言語ごとに発音が独特ですが、英語、フランス語やドイツ語式に発音しないように特に注意します。また th も英語式に発音してはなりません。
q はフランス語と同じように常に qu+母音の形で用いられ、[kw]の発音になります。同じように gu の場合も[gw]の発音になります。
例:aqua(アクワ)、ambiguus(アムビグウス)
h は、フランス語やスペイン語のように無音(サイレント)ではなく常に発音されます。日本語のハ行の音です。
例:humor(フーモル)
s は常に清音の発音で、ドイツ語のように濁音にはなりません。
例:saurus(サウルス(ザウルスと発音しない))
W の文字はラテン語にはありませんが、外国語の固有名詞に由来する学名に使用することは可能で、読み方はその固有の発音によります。
例:woodwardi(ウッドワーディ)、welchi(ベルヒ)
上に解説した以外の子音については通常のローマ字読みの発音でほぼ差し支えありません。
音量(母音の長短)
ラテン語の母音には短音と長音があり、長音は短音の約2倍の音量(長さ)を持つといわれます。長音には本質的に長い自然長音(long by nature)と、母音の後に子音が連続あるいは複子音が来ることによって長くなる位置長音(long by position)があります。自然長音の場合は一定の規則がないので、わからない場合にはラテン語の辞書で調べる必要があります。
音節とアクセント
音節は、アクセントの位置を決定するのに重要な役割を持ちます。1音節は1母音(複母音も1音節とみなす)を元にして作られます。分節(articulation)するには、原則として母音で区切り、最後に残った子音はその前の母音に付けます。ラテン語の単語のアクセントの付け方は容易で、以下の規則に従います。
- 単音節の単語はアクセントがありません。
- 二音節の単語は最初の音節にアクセントがあります。
- 三音節以上の単語では、最後から二番目の音節が長い場合にはその音節にアクセントが付き、短い場合にはその前の音節(最後から三番目の音節)にアクセントが付きます。
ハイフネーション
印刷物のゲラ刷りをチェックする際に注意なければならないことのひとつに、欧米語のハイフネーションがあります。英単語なら辞書を引けば区切れる位置が示されているので、それに従ってハイフンで分割すればよいのですが、ラテン語である学名を分割する場合、どの位置にハイフンを設定するか迷った方も少なくないかと思います。前述のように、ラテン語は音節で分節されるので、以下に示すように基本的に音節の切れ目に従って区切る(ハイフネーションする)ということになります。1. 母音+子音+母音の場合:
子音は後ろの母音に付きます。
例:CAE-SAR、RU-BI-CO-NE、SU-PE-RA-TO
2. 母音+子音+子音+母音の場合:
① 二つの子音を分割して前後の母音に付けます。
例:COM-MI-LI-TO-NES(M-M)、A-RI-MI-NEN-SI(N-S)
② 二つの子音が黙音(p、b、t、d、c、g)+流音(l、r)ならば、分割しないで後ろの母音に付けます。また、二つの子音が語頭に立ち得る子音(sp、st、sc、fl、fr 等)の場合も同様です。
例:A-DLO-CU-TUS(D+L)、SUG-GE-STUM(ST)
3. 子音が三つ以上連続する場合:
上記の①、②に基づいて区切りますが、一般的には連続する子音の最初のものと残りを分ける(子音-(子音+子音))のが普通です。
例:NO-VEM-BRIS
これらの区切り方は原則的なもので、実際には語の形成過程や音韻等を考慮して分割しますが、ハイフネーションに際してはこの原則に従えばよいでしょう。
外国語の固有名詞に由来する学名
学名の読み方は前述のようにラテン語の読み方に従いますが、近代の固有名詞に由来する語の場合は例外で、それぞれもとの固有名詞の発音に従います。以下に例を示します。
学 名 由来する固有名詞 読み方 Reuteria Reuter ロイテリア leuckarti Leuckart ロイッカルティ zacheri Zacher ツァッヘリ Bougainvillea Bougainville ブーゲンビレア harmandi Harmand アルマンディ bordeausiacus Bordeaux ボルドーシアクス valenciennii Valenciennes バランシヤンニイ investigatoris Investigator インベスティゲイトリス chosenensis 朝鮮 チョーセネンシス
ギリシャ語に由来する学名
学名にはギリシャ語由来の語も多いですが、ラテン語化して書かれているので読み方とアクセントは上記の規則に従います。ただし母音の長短についてはギリシャ語の辞書から探すことになります。
誤った学名の読み方
細菌類やプランクトン類は和名がないものが多く、学名のカタカナ表記が和名的に用いられますが、一般に通用している読み方で正しくないものも少なくありません。以下にいくつか例を示します。
分類群 学 名 誤った読み方 正しい読み方 硅藻 Coscinodiscus コシノディスカス コスキノディスクス 硅藻 Chaetoceros キートセロス カエトケロス 硅藻 Eucampia ユーカンピア エウカムピア 鞭毛虫 Euglena ユーグレナ エウグレナ 渦鞭毛藻 Gymnodinium ギムノディニウム ギュムノディニウム 渦鞭毛藻 Ceratium セラチウム ケラティウム 渦鞭毛藻 Goniaulax ゴニオラックス ゴニアウラクス ハプト藻 Pavlova パブロバ パウロワ 緑藻 Volvox ボルボックス ウォルウォクス 細菌 Bacillus バチルス バキルルス 細菌 Vibrio ビブリオ ウィブリオ 細菌 Pseudomonas シュードモナス プセウドモナス 細菌 Aeromonas エロモナス アエロモナス 細菌 salmonicida サルモニサイダ サルモニキダ 化石巻貝 Vicarya ビカリヤ ウィカリュア 恐竜 Tyrannosaurus ティラノサウルス テュランノサウルス
学名の読み方に関する付記
この節では学名の読み方について解説してきましたが、残念なことに実際には正しい学名の読み方をされることはほとんどありません。それは、日本の大学では分類学を専門に教育研究する学科や講座であってもラテン語について教えるところは皆無に等しいからです。
かなり以前の話になりますが、日本魚類学会の学会発表で、アメリカのある研究者がエイ類の分類に関する発表をしたときのことです。発表に対する質疑応答で、日本人のある質問者が発表者との英語でのやりとりの中で、メガネカスベ属の属名の Raja を“ラジャ”と発音していました。すると発表者はそれを逐一“ラーヤ”と正しいラテン語の発音にあらためていましたが、それでもその日本人の質問者は頑強に“ラジャ”と最後まで発音し通し、同じ日本人として恥ずかしい思いをしたことがありました。この質問者に、アカエイの種小名の akajei をどう発音するのか訊いてみたいと思いました。
おそらく発表者のアメリカ人研究者はしっかりしたラテン語教育を受けていたものと思いますが、しかし実際には、国際会議の席上でも欧米の研究者たちにラテン語の正しい読み方がほとんどできていないのが実情です(専ら完全な英語読みになっている)。これは、日本だけでなく欧米でもラテン語教育がしだいにおろそかになっている現れと思われます。
ある細菌の属名に Pseudomonas というのがありますが、これをアメリカ人は“シュードモナス”、ドイツ人は“プソイドモナス”と発音します。そのどちらも正しくないのは言うまでもありませんが、とにかく、学名を銘々好き勝手に読んでいたのでは学会発表での質疑応答もままなりません。
またあるときは、ある水産高校の若い先生がマサバの学名 Scomber japonicus を“スコンバー ジャポニカス”と得意げに生徒に堂々と教えていた現場を見たこともあります(正しくはスコームベル ヤポニクス)。日本では教育の現場ですらこのありさまですから、正確なラテン語の読み方を期待するのは現実とほど遠いのかも知れません。
ラテン語が正しく読まれないのは、現代の国際語である英語の影響が大きいでしょう。数あるヨーロッパの言語の中で、英語の綴り字の読み方はローマ字の読み方と最もかけ離れていると言われます。
私は以前、日本に研修に来たあるメキシコ人たち(母国語はスペイン語)と数ヶ月にわたってつきあい、日常会話を英語でしていたことがあります。彼らはある程度の英語能力はあるものの、しばしば cutter をクッター、corn をコルン、air port をアイル ポルト、also をアルソーなどとスペイン語式に発音し、会話の理解に苦労させられたことがありました。
また別のエピソードを挙げましょう。私は沖縄が好きで、たびたび訪れましたが、あるときそこで若いアメリカ人女性の旅行者に会いました。いろいろ世間話をしていると、彼女はそれ以前にも日本に来たことがあるそうで、日本でどこどこに行ったかと尋ねてみると、彼女は“イーハイム”というところに行ったことがあると答えました。日本にそんなところはないだろうと、その綴りを訊いてみると“E H I M E”。なるほどと思いましたが、英語式読みの特殊性を再認識させられました。
しばしば英語式に読まれる学名ですが、それではラテン語本来の発音とほど遠くなり、英語式の読み方を他言語に適用してはならないことがわかるでしょう。最近のあるウミウシ図鑑で、“学名はラテン語式に読んでも英語式に読んでもどちらでもよい”と解説されていたりしますが、このような見解は全く支持できないと言わざるを得ません。学名を英語式に読むのは、“E H I M E”を“イーハイム”と読むのと同じことです。
学名にラテン語が用いられるのは、リンネ式学名の創立当時に国際語でありその国際的中立性が支持されたからです。ラテン語は既に死語になっているとはいえ(厳密に言えば、現在でもバチカン市国の公用語として使われている)、後述するように命名規約においては属名と種小名の性の一致の原則や、科グループ名の作り方の規則、固有名詞のラテン語化の規則など、明らかに生きた言語として扱われています。生きた言語である以上、その本来の発音を尊重し、学名の読み方もラテン語の規則に忠実に従うべきと考えます。そして、学名が世界共通のものであるためには、読み方も世界共通にしなければならなのは自明の理でしょう。
世の中の生物学者には、学名を分類群識別のための文字コードのように捉えてその読み方にまで頓着しない人もいるようですが、学名は識別記号ではなく(単語として発音できない文字列の組み合わせは学名と認められない)生きた言語であるということを認識していただきたいものだと思います。
種名における二名法
種名の表記には属名(generic name)と種小名(specific name)から成る二名法(nomenclator binominalis)が用いられます。例えば、ヒトの学名は Homo sapiens ですが、Homo が属名で sapiens が種小名になり、このふたつが揃ってはじめて学名の構成要件を満たし、正式な種名(species name)として扱われます。かなりわかりやすく言えば、属名が“苗字”で種小名が“名前”と考えれば理解しやすいでしょう。つまり、系統的に近い“親戚一同”は同じ苗字を持つ(同属)というわけです。先ほどのヒトの例で言えば、ヒトと同属の現生種はいませんが、北京原人やジャワ原人などの原人類の学名は Homo erectus であり、これらは同じ属の“親戚”であると言えるでしょう。しかしそれよりも古い猿人になると別属の Australopithecus に分類され、現代人との類縁関係は遠いことがわかります。
二名法の起源については前に述べましたが、属名はラテン語またはギリシャ語の単数形の名詞、種小名は同じく形容詞または属格の名詞であり、修飾⇔被修飾の関係になります。現在のラテン系諸言語では多くの場合名詞の後に形容詞が来ますが、その語順と同じと思えばいいでしょう。ヒトの学名の Homo sapiens で説明すれば、Homo ホモー)が名詞で“人”、sapiens (サピエーンス)が分詞形容詞で“賢明な”という意味になります。またイヌ Canis familiaris の場合は Canis (カニス) が名詞で“犬”、familiaris (ファミリアーリス)が形容詞で“家族の”という意味になります。なお植物の命名規約では種小名ではなく種形容語(specific epithet)と呼ばれますが、全く構造通りの呼び方です。
種名を綴る場合、属名は語頭が必ず大文字になり、種小名はすべて小文字になります。種小名が人名や地名等の固有名詞に由来する場合でも語頭は小文字です。これは、トゥルヌフォールが種を表現するのにあたかもラテン語の文章のように表現したことに由来するものと思われます。種名(亜属名、亜種小名を含む)は通常、イタリック体(斜体)字で綴られます。
属名、種名とも2文字以上からなるラテン語またはギリシャ語の一語、あるいはいくつかの単語からなる複合語から成ることとされ、中に“?”や“&”などの記号や数字を含んではなりません。数を示したい場合はラテン語またはギリシャ語の数詞を用い、例えば1なら uni(ラテン語)または mono(ギリシャ語)、2なら bi(ラテン語)または di(ギリシャ語)を使います。
また、前述のようにラテン語やギリシャ語以外の言語(フランス語、中国語等)に由来するものでも発音をラテン語のアルファベットで表わせば学名とできます。さらに、意味を持たない任意の文字の組み合わせでもかまわないことになっていますが(新造のラテン語と見なす)、この場合は単語として使用するために形成したものという条件があります(例えば“cbafdg”や“ztqidk”のような任意組み合わせは到底発音できないので不可)。
属名と種小名の性の一致
ラテン語やギリシャ語では名詞には性(gender)があり、男性(masculine)、女性(feminine)、中性(neuter)のいずれかの属性になります。名詞を修飾する形容詞は被修飾語の性によって語尾が変化します。この文法的特徴は現在のラテン系諸言語にも受け継がれています。学名についてもこの文法が適用され、名詞である属名はすべて性の属性が決まっていて、それを修飾する種小名の語尾は属名の性と必ず一致しなければなりません。これは動物、植物、細菌のすべての国際命名規約で規定されているルールです。
しかし、ラテン語やギリシャ語の名詞には共通性(common gender)のものや、また古典語には男性と女性の両方の性を持つものもあります。そのような単語が属名に用いられた場合は命名者が指定した性が採用され、指定がない場合には男性として扱われます。前述のヒトの属名の Homo やイヌの属名の Canis は共通性の名詞ですが、命名したリンネが性を指定していないのでいずれも男性として扱われています。また、ラテン語やギリシャ語以外から作られた属名についても同様の扱いとなります。なお、いくつかの単語の複合語から成る属名の場合は最後にくる名詞の性になります。
日本産の生物には“日本の”という意味の形容詞である japonicus(ヤポーニクス)という種小名が多く付けられていますが、これは男性形で、女性形では japonica(ヤポーニカ)、中性形では japonicum(ヤポーニクム)となります。例を挙げれば、スズキ Lateolabrax japonicus(男性形)、ホタルジャコ Acropoma japonicum(中性形)、カタクチイワシ Engraulis japonica(女性形)など、種小名の意味はすべて同じですが、属名の性に従って語尾変化が異なるものです。この japonicus のように男性形が“~us”、女性形が“~a”、中性形が“~um”の変化をする形容詞が多いですが、もちろんそれ以外の形の変化をする形容詞もいろいろあります。
分類の見直しによってある種の属名が変更された場合は、新しい属名の性に従って種小名の語尾も変えねばならず、これを命名法上の強制変更(mandatory change)といいます。ところが実際には、それを行なうべき分類学者がラテン語やギリシャ語について明るくないために、変更しなければならない場合がされずに放置されたり、誤った変更をされることが往々にしてあります。例えば、マイワシの学名として Sardinopus melanosticta が長らく用いられてきましたが、これは実は属名の Sardinopus は男性形で種小名の melanosticta は女性形です。最近になってようやく種小名が男性形の melanostictus に変更されましたが、このような事例は現行の図鑑類などでも多々見受けられるそうです。また、カタクチイワシの学名は最近ではなぜか Engraulis japonicus と綴られますが、これは属名の Engraulis が女性形で種小名の japonicus が男性形の誤った形式です。
このように、種小名が形容詞または分詞形容詞の場合には属名の性に必ず一致して語尾変化をしますが、種小名が名詞の場合には属名が変更されたとしても当然ながら形は変化しません。種小名が形容詞か名詞かを判断するにはラテン語やギリシャ語の辞書で調べなければなりません。
特にギリシャ語由来の名詞にはラテン語の形容詞と綴りの似たものがありますから注意が必要です。例えば、ドチザメのは学名は Triakis scyllium ですが、属名の Triakis は女性形で、種小名の scyllium は語尾からするとラテン語の形容詞の中性形ように見え、属名の性と一致していないように感じられます。実際、それを“考慮”して Triakis scyllia としている文献もあります。しかし実は scyllium は形容詞ではなくギリシャ語に由来する名詞なので、この学名に不都合はないということになります。
亜種名における三名法
前述のように種名の表記には属名と種小名から成る二名法が用いられますが、亜種(subspecies)の場合は種小名の後にさらに亜種小名(subspecific name)を付けた三名法(nomenclator trinominalis)になります。
亜種というものは、種レベルでは同じなのに形態的、生態的に微妙に異なる、主に地域集団に対して命名されます。ですから、ある既存の種をいくつかに分ける場合に亜種というものが発生するわけです。
以下にいくつかの例を示します。北米大陸にオオクチバス Micropterus salmoides という淡水魚が生息していますが、この種のフロリダ半島に生息する集団は生物学的に少し異なることがわかって別亜種のフロリダバスとして記載(発表)されました。その場合の亜種名は Micropterus salmoides floridanus となり、オオクチバスの学名の後にフロリダバスの亜種小名を付け足したものになります。
フロリダ半島以外に分布するオオクチバスをそれに対比させて亜種名で示す場合は、元の種小名を重ねて Micropterus salmoides salmoides となり、これはフロリダバスに対して一般にノーザンバスと呼ばれます。これを亜種に対して模式亜種(type subspecies)あるいは担名基準亜種(name-bearing subspecies)といい、種(この場合は Micropterus salmoides )の模式標本(type specimen)を含む亜種が必ず模式亜種になります。
図鑑等でこのような三名法で書かれた学名の種があれば、必ずその亜種または模式亜種が存在することがわかります。オオクチバスの場合、単に Micropterus salmoides と二名法で表記されていれば、広義ではノーザンバスとフロリダバスの両方を含むことになります。
また仮に、分類の見直しによってフロリダバスが種に昇格することがあれば、亜種小名が種小名に昇格してその種名は Micropterus floridanus となります。その“種”の命名者は分類の見直しを行なった人ではなくフロリダバスを亜種として記載した人になり、記載した日はフロリダバスが種に昇格した日ではなく亜種として記載された日になります。命名者と記載日は後述する学名の先取権の問題に関して非常に重要になります。
汎世界的に分布するイノシシの場合は27もの亜種があると言われます。その中でリンネが Sus scrofa の学名を命名した基準となったヨーロッパ産のものが模式亜種(ヨーロッパイノシシ)となり、日本には、日本本土に生息するニホンイノシシと琉球列島に生息するリュウキュウイノシシの2亜種が分布します。
昆虫のマイマイカブリの場合も、マイマイカブリが模式亜種で日本産のものだけでも実に多くの亜種があります。これらは種レベルではすべて同一ということになり、模式亜種であるマイマイカブリに種の模式標本があることがわかります。
なお、亜種小名もそれが形容詞や分詞の場合には、種小名の場合と同様に属名の性に従って語尾変化をさせなければなりません。
種 オオクチバス Micropterus salmoides 亜種 ノーザンバス Micropterus salmoides salmoides ←模式亜種 フロリダバス Micropterus salmoides floridanus
種 イノシシ Sus scrofa 亜種 ヨーロッパイノシシ Sus scrofa scrofa ←模式亜種 ニホンイノシシ Sus scrofa leucomystax リュウキュウイノシシ Sus scrofa riukiuanus
種 マイマイカブリ Damaster blaptoides 亜種 マイマイカブリ Damaster blaptoides blaptoides ←模式亜種 エゾマイマイカブリ Damaster blaptoides rugipennis キタマイマイカブリ Damaster blaptoides viridipennis コアオマイマイカブリ Damaster blaptoides babaianus アオマイマイカブリ Damaster blaptoides fortune ナゴヤマイマイカブリ Damaster blaptoides paraoxuroides ヒメマイマイカブリ Damaster blaptoides oxuroides サドマイマイカブリ Damaster blaptoides capito コマイマイカブリ Damaster blaptoides leuisi
亜種より下のカテゴリー
亜種よりさらに下に、変種(variety)、型(form)、遺伝的多型(morph)、品種(race)、突然変異型(mutant)、季節型(seasonal form)などさまざまなカテゴリーが区別されて命名されることがあります。しかしこれらのカテゴリーは動物命名規約では適用外に置かれます(植物では命名規約の範疇に置かれる)。
これは、これらの名称を禁止するというわけではなく、動物の学名としての適格性を有しないというだけであって、季節型、遺伝型、生態型などを特定の名称で呼ぶことが便利であるなら命名することは自由です。
また仮に、分類の見直しによって例えば型が亜種に昇格することがあれば、型の名前が亜種小名に昇格します。その“亜種”の命名者は型名の命名者ではなく分類の見直しを行なった人になり、記載日は型が発表された日ではなく亜種に昇格した日になります。つまり、命名規約の適用を受けていなかったカテゴリーが命名規約の範疇に入った時点から命名者や記載日の概念が発生するというわけで、この点は亜種が種に昇格する場合と扱いが異なるので注意が必要です。
これらのカテゴリーにおける名前は種小名と同様にイタリック体で書いてよいことになっていますが、亜種の表記と区別するためにローマン体の var.、forma などを名称の前に付けます。なお、このような“型”などに対して和名が与えられていることがありますが(下のハナワイモ類など)、これは便宜上のことであり、分類学上の種としては認められません。
以下に記述例を示します。
アワジチヒロガイ Volachlamys hirasei アワジチヒロ型 Volachlamys hirasei var. awajiensis ヤミノニシキ型 Volachlamys hirasei var. ecostata
ハナワイモ Virroconus sponsalis forma sponsalis シロセイロンイモ Virroconus sponsalis forma nanus セイロンイモ Virroconus sponsalis forma ceylanensis
亜属名
亜属(subgenus)は属と種の間の分類区分で、これを表記するには属名と種名の間に円括弧書きで挿入し、属名の場合と同様に語頭は大文字になります。命名規約では属名と亜属名をひっくるめて属階級群名(generic-group name)と呼び、これらは共通の性でなければならないことになっています。
ある属に複数の種が含まれる場合にはその属を代表する1種を模式種(type species)に指定し、その属に亜属を創設する場合、模式種の属する亜属は模式亜属(type subspecies)となり、属名と同じ亜属名になります。一方、模式種の属するのと別のグループに対して新たな亜属名が与えられることになります。
模式種は、新しい属を創設した人が指定すればその種が模式種となります。属を創設した人が模式種を指定していない場合は、のちの人がその属の中から任意の種を選んで模式種にすることができます。ある属が創設されたときにその属に含まれる種が1種しかなく、のちに複数の種が含まれるようになった場合には最初の種が模式種と見なされます。
以下に亜属の記述例を示しますが、亜属名は種名の表記に不可欠なものではなく、分類以外の論文などでは省略されることが多いです。
属名 亜属名 種小名 オオミツバチ Apis (Megapis) dorsata セイヨウミツバチ Apis (Apis) mellifera
種の命名者
種の命名者は、しかるべき印刷物にその種を新種として発表した人で、命名規約の用語では著者(author)と呼ばれ、論文などで新種発表することを記載(description)といいます。
学名を印刷物等に引用する場合、命名者名は種の学名の後にコンマなどの記号を挿入せずに続けて記述し、種名と区別するためにローマン体(ブロック体)で綴ります。命名者名は姓(family name)のみを記載し、すべてラテン文字で綴ります。通常ラテン文字によらない表記の人名(日本人、アラビア人、ロシア人等)の場合はその発音をなるべく正確にラテン文字で表音します。前述のように学名には記号付き特殊文字の使用は認められていませんが、命名者名の場合はその限りではありません。命名者名は学名の一部ではなく、省略してもかまわないことになっていますが、分類の論文では命名者名と記載年(新種発表の論文が刊行された年)は極めて重要であり必ず表記される習慣になっています。記載年は、命名者名の後にコンマで区切って付け加えます。
命名者は必ずしも一人ではなく、二人あるいは三人以上が共同で記載論文を発表して命名者になることもあります。そのような場合、二人の場合は A and B または A & B、三人以上の場合は第一著者の名前に続けて“et al.”という用語を用いて示すことができます。“et al.”というのはラテン語の“et alii”の略で、英訳すれば“and others”となり、学術論文でも文献の引用時によく用いられます。
ある種が最初に記載されたときの属名が変更、あるいはその種が別属に移された場合には、命名者名を円括弧に入れて表記します。逆に言えば、命名者名が括弧に入っていればその学名は元々の属名ではないということがわかるわけです。前述のシーボルトのファウナ・ヤポーニカ「魚類編」で新種記載された魚種をいくつか例に挙げます。
アユ Plecoglossus altivelis Temminck and Schlegel ウナギ Anguilla japonica Temminck and Schlegel マダイ Pagrus major (Temminck and Schlegel) ヒラメ Paralichthys olivaceus (Temminck and Schlegel)
上のふたつは命名者名が括弧に入っていないので新種記載されたときそのままの学名で、下のふたつは命名者名が括弧に入っているので記載後に属名が変更されたことがわかります。印刷物の編集者などがこの規則を知らずに体裁の統一を図るためにすべて括弧を取ったりあるいは付けたりすることがありますが、それは大きな誤りです。また分類を専門としない生物学者にとっても、この規則も含めて学名についてもっと理解を深めるべきでしょう。
以前は、著名な命名者の名前は略して表記されましたが(例えば Linné は L.、Temminck and Schlegel は T. & S.)、近年では命名者の数がどんどん増加して略字ではわかりにくくなってきたので、略さずに命名者の姓(family name)のすべてを綴るように命名規約で勧告されています。
種名の表記法
以上説明した種名の表記法について、セイヨウミツバチの学名の例を以下に示しました。
① Apis mellifera
② Apis mellifera Linnaeus
③ Apis mellifera Linnaeus, 1758
④ Apis mellifera mellifera
⑤ Apis(Apis)mellifera
⑥ Apis(Apis)mellifera mellifera
⑦ Apis(Apis)mellifera mellifera Linnaeus, 1758
①~⑦のすべてが容認される書き方ですが、必要最低限の要素による①が最も簡単でかつ最もよく用いられる書き方です。また、分類の論文では命名者名を付記した②もよく用いられ、さらに詳細に記載年を加えたのが③です。④は亜種名、⑤は亜属名、⑥はその両方を示すときの書き方です。⑦は種名に付随するすべての要素を示したものですが、通常ここまで詳しく表記されることはありません。
ところで分類以外の通常の論文中で、研究材料に用いた生物名の学名を示す際に、命名者(②の例)、記載年(③の例)、また亜属名(⑤の例)まで付記されていることがあります。もしかしたら、学名にこのような“装飾”をつけるとかっこよく見えるから好まれるのかも知れませんが、しかし、属名と種小名だけで種の特定はできるので、それ以外の要素の付記は分類以外の論文では全く不要です。
なお、論文等で同じ種の学名が繰り返し何度も出てくる場合には二度目以降は属名を略記してもよいことになっています。例えばマダイ Pagrus major の場合は P. major となります。マダイ Pagrus major とアユ Plecoglossus altivelis など同じ頭文字の属名の種がひとつの論文に登場する場合、これらを区別するために、Pa. major、Pl. altivelis のような略記になります。なお細かいことですが、属名の後のピリオドはイタリック体になりません。
ただし、最初からいきなり略記してはならず、最初に学名が登場するときには必ず属名と種小名をフル表記(spell out)しなけばなりません。同様に、学名が文頭に来る場合には、既出の学名であっても属名をフル表記しなければなりません(学名に限らず文頭では単語の略記をしないというのが欧文での原則)。また、略記できるのは属名だけであり、種小名はどんなに長い綴りでも省略して書くことはできません。しかし亜種を論じる場合はこの限りではなく、例えば前述のオオクチバスの場合で2亜種がひとつの論文に登場するとき、ノーザンバスを M. s. salmoides、フロリダバスを M. s. floridanus と表記できます。
未記載種(新種)と思われるある種の存在がわかったとき、正式に新種記載されるまでの間、その種が属すると思われる属名とその後に“sp.”を付けてとりあえず種名の代わりに用いることが多いです。例えばホシスズキ Lateolabrax sp.、チュウゴクアカガイ Scapharca sp.、ズベタイラギ Atrina sp. など。“sp.”は種を意味するラテン語の species(スペキエース)の略語で、種小名ではありませんからイタリック体ではなくローマン体で綴ります。同じ属で複数の未記載種あるいは不明種の存在を示す場合には“spp.”となります。
科グループの学名
科グループ(family-group)には、上科(superfamity)、科(famity)、亜科(subfamity)、族(tribe)、亜族(subtribe)が含まれ、一名式(uninominal)のラテン語で表わされます。属名以下の学名がイタリック体で表記されるのに対して、科グループ以上の学名は通常ローマン体で表記され、語頭は大文字になります。
これら科グループの学名は自由に作ることはできず、必ずその科グループの模式属(type genus)の属名から作ることが命名規約で規定されています。国際動物命名規約では、科名の場合、模式属名の属格活用形の語幹に“~idae”という語尾を付けて作ります(植物、細菌では“~aceae”)。同様に、上科は“~oidea”、亜科は“~inae”(植物、細菌では“~oideae”)、族は“~ini”(植物、細菌では“~eae”)、亜族は“~ina”(植物、細菌では“~inae”)という語尾になります。
属名の語幹はラテン語またはギリシャ語の文法規則によって決まっていて、単純に属名の語幹だけをとる場合や属名にはない文字が現れる場合などさまざまです。以下に動物の科名の例を示しますが、科以外の分類群名も科の場合と全く同じ語幹をとります。
Apis(ミツバチ属) → Apidae(ハチ科) Canis(イヌ属) → Canidae(イヌ科) Sparus(ヘダイ属) → Sparidae(タイ科) Culex(イエカ属) → Culicidae(カ科) Homo(ヒト属) → Hominidae(ヒト科) Caranx(ギンガメアジ属) → Carangidae(アジ科) Chaetodon(チョウチョウウオ属) → Chaetodontidae(チョウチョウウオ科) Conger(クロアナゴ属) → Congridae(アナゴ科)
ある人が、科グループに科や族などの新たな分類階級(taxon)を創設しようとする場合、その人はその科グループに属する任意の属を模式属に選ぶことができます。その属がその科グループにおける最も古い属である必要はありませんが、可能な限り有名かつその科を代表する属を選ぶべきであると命名規約で勧告されています。
模式属がはっきりしない場合、模式属をどれにするかの見解の相違によって同じ科でも異なった学名が用いられることがあります。
ところで、科名のラテン語学名は学会発表の場などでよく出てきますが、例えば、ネコ科(Felidae)は“フェリデー”、ベラ科(Labridae)は“ラブリデー”と、しばしば語尾が英語式に発音されます。しかしこれらは誤りで、「学名の読み方」のところで解説したように、重母音の“ae”はローマ字そのままに読むので、“フェリダエ”、“ラブリダエ”と発音せねばなりません。漫画や映画で知られる「テルマエ・ロマエ」(TERMAE ROMAE)は、ラテン語の読み方を正確に表現していると言えます。
科グループより上位の分類階級
科グループより上位には門(phylum)、綱(class)、目(order)の分類階級がありますが、前述のようにこれらの階級群は命名規約の規制を受けませんから基本的に自由に命名できます。これらの名称は一般にラテン語またはラテン語化した語を用い、常に複数形で語頭は大文字にすることになっています。植物や細菌の命名規約ではこれらのカテゴリーにおける名称の語尾にも規定があって、前述の科グループの場合と同様に分類階級によってそれぞれ語尾が決まっていますが、動物の場合は自由です。
後述するように、命名規約が規制する科グループから種グループまでの分類階級では同名の分類単位(同名の種や同名の科)が両立することは許されませんが、規約の規制を受けない科グループより上位や亜種より下のカテゴリーにはその原則は適用されません。例えば、節足動物の甲殻綱と軟体動物の頭足綱に同じ Decapoda という目があって、これを日本語では甲殻類の方を十脚目(エビ、カニ類など)、頭足類の方を十腕形目(タコ類)と呼んで区別しています。
なお、科グループより上位の分類階級における名称は、命名規約の規制を受ける階級の学名と区別するために厳密な意味では学名と呼ばないとする意見もあります。
学名の発表
未知の生物が発見されると、学者はそれに学名を付けて世間に発表(報告)します。この行為を記載(description)といいます。学術的に記載されていない(と推定される)種は未記載種(undescribed species)と呼ばれます。例えばある未開の地域に生息する生物が、その場所ではよく知られた通称で呼ばれていたとしても、しかるべき手続きによって学名が与えられるまでは学術的には未記載種となります。シーボルトがやってきた時代の日本がまさにそうで、マダイやヒラメなど“未記載種”ばかりでした。
未記載種に学名が与えられて公式な印刷物に公表されると、これが新種(new species)ということになります。巷では“未記載種”と“新種”が混同されていて、新聞記事などで、学名が与えられる前の段階のものを“新種”と表現していたりしますが、それは正確な表現ではありません。
この新種の場合も含めて、新属、新科などの学名を発表するには、世間によく流布している印刷物に公表しなけばなりません。印刷物というのは学術雑誌や書籍のことであり、学位論文や学会等での講演要旨などは印刷物と認められません。学名を発表する場合、のちの混乱を避けるために、新属ならば模式種、新科ならば模式属をその著作物の著者が指定すべきです。新種の場合は後述する模式標本を指定することが必須となります。
新種発表の場合、最も一般的なパターンは学術定期刊行物に記載論文を投稿することです。論文の構成は、模式標本の写真と絵、その種の分類学上の位置付け、その種の詳細な記載文、シノニムリスト(文献)などから成ります。絵を添えるのは、写真だけでは細かい場所までの描写がどうしても不十分になるからで、点描による標本の緻密な描写が要求されます。記載文の言語についての規定は特にありませんが、現代の国際語である英語でなければほとんどの学術雑誌は論文の投稿自体を受け付けてくれません。それに加えて、ラテン語、フランス語、ドイツ語等による副文を添えることが推奨されています。
ところで、ある種が未記載であるという確証を得ることは実は非常に難しいことで、例えば新種記載論文が印刷されたあとでその種が以前に別の名前で記載されていたことが判明することもよくあります。その場合には後述のように学名を変更しなければなりませんから、新種記載をしようとする場合にはとにかく十二分な文献(近似種の記載論文)の調査が必要になります。
ときどきテレビ等で、未開のジャングルに生息する昆虫や深海に生息する生物の新種探しと銘打った番組があり、画面に「新種発見!」というテロップが踊っているのを見ることがあります。しかし、種の同定というものは前述のように慎重かつ膨大な分類学的検証作業によってようやく新種であるという結論が得られるわけであり、調査が進んでいない場所でこれまでに見たことがない生物を見つけたとしても、それを一見して新種と即断できることはあり得ません。
同名の回避と先取権の原則
国際命名規約ができたそもそもの目的は同名関係の状況を避けるためです。同名関係というのは、前述のように同じタクソン(科や種)に違う名前が付けられる同物異名(synonym)と、逆に違うタクソンが同じ名前を持つ異物同名(homonym)をいいます。
これを避けるためには、ひとつのタクソンには有効なただひとつの学名を認めるという原則が必要になり、その運用は和名や英名の場合のように曖昧であってはなりません。それを遵守するための規則が“先取権の原則”で、これはあるタクソンの学名について、最も古く発表されたものが唯一有効であるという単純明快な原則です。
同じ種が違う学名で何度か記載された場合(同物異名)、わずか1日でも早く発表された学名が唯一有効とされます(同じ雑誌の同じ号に発表された場合はページの若い方に先取権がある)。また、あるタクソンAに付けた学名が既に別のタクソンBの有効な学名として使われていることが判明した場合(異物同名)は、その学名はタクソンAの名称として使うことができず、タクソンAに対しては別の新たな学名を付けなければなりません。
一旦新種として記載された学名は、たとえそれが綴り間違いや差別的な意味の語であってもそのことを理由に学名を変更することはできません。それは命名者自信も例外ではなく、自分の付けた学名に問題が発見されたとしても本人でさえそれを変えることはできないのです。
ただし動物命名規約では先取権の原則に例外があって、最も古い学名であってもその存在を忘れ去られてしまって最近50年間に全く印刷物に用いられていないものは遺失名(nomen oblitum)として破棄することができ、よく通用している新しい学名を有効名としてもよいということになっています。植物、細菌ではこの例外規定はありません。
このように、世の中に同じ種名の生物は存在しないわけですが、ただし種小名が同じ種はかなり多く存在します。例えば前述の japonicus、japonica、japonicum という種小名の種は魚類だけもかなり多いです。しかしそれらは属名が異なるために別の種名になります。
これは、コンピューターのフォルダー階層構造と全く同じことで、フォルダー名が属名でファイル名が種小名と同じと考えればよくわかるでしょう。同じファイル名でもフォルダーが違えば存在できますが、同じところに入れようとするとどちらかのファイル名を変えなければなりません。
ところで、動物、植物、細菌はそれぞれ独立した命名規約に規制されるので、界(kingdom)が違って同じ分類階級に同名のタクソンが存在することを禁じる規則は今のところありません。実際、動物と植物に同じ属名がいくつか存在し、例えば Pieris(動物では昆虫のシロチョウ科のモンシロチョウ属、植物ではツツジ科のアセビ属)や Limnophila(動物では昆虫のヒメガガンボ属、植物ではゴマノハグサ科のキクモ属)などがあります。属名も種小名も同じ全く同一の種名は今のところないようですが、とにかく同名関係は好ましいことではないので今後分類群を超えての調整が必要でしょう。
模式標本
新種の発表には必ずその種の根拠となる標本の指定を伴わなければなりません。それを完模式標本(holotype)といって必ず1個体の標本が指定されます。なぜ1個体かというと、仮に複数の個体を模式標本に指定した場合、その後の研究によってそれが実は複数の種から成ることが判明すると、種の学名を担う標本として使えなくなってしまうからです。
新種発表する際に材料となる標本が1個体しかない場合は完模式標本しか作れませんが、複数の個体がある場合には副模式標本(paratype)も指定します。これは記載のための参考となる標本で、何個体指定してもかまいません。模式標本と副模式標本を合わせて模式系列(type series)と呼び、記載文には通常すべての模式系列標本のデータが記述されます。
なお、近年では1個体の標本のみに基づく新種記載はかなりためらわれる傾向にあります。形態的に既知種と明らかに異なる個体が発見されても、それが1個体だけならば雑種や突然変異個体である可能性がかなり疑われるからです。
完模式標本が何らかの理由で紛失あるいは消失した場合(戦時下の国では戦火で焼失したことがよくあった)には、新模式標本(neotype)を新たに指定することができます。この場合、最初に記載されたときに副模式標本が指定されている場合にはその中から1個体が選ばれるのが普通です。ただしこれは完模式標本が喪失した明らかな証拠がある場合に限られ、単に完模式標本の所在が不明な場合などにむやみに新模式標本の指定ができるわけではありません。
以前には、複数の標本に基づいて新種記載が行なわれ、完模式標本が指定されなかったことがよくありました。そのような標本群を総模式標本(syntype)といいますが、これはその記載論文中で引用されたすべての標本を意味し、実際の標本ばかりでなくその種を示す絵や写真等も総模式標本の構成要素となります。ただ、前述のようにこのような標本の指定方法は好ましくないので、のちの研究者が総模式標本の中から1標本を種の代表として指定することができます。それを後模式標本(lectotype)といい、総模式標本中のその他のものは副後模式標本(paralectotype)となります。後模式標本は、一旦ある人によって指定されると変更することはできず、完模式標本と同等の扱いを受けます。一連の総模式標本が複数の種から成ることが判明した場合に、後模式標本が指定されていれば分類の混乱を避けることができます。
また、カブトムシやオシドリなど雌雄で形態に著しい差がある生物もありますが、このような場合でも完模式標本はいずれかの性の1個体です。しかし種の全体像を把握するために模式標本と別性の標本があると便利なので、別性の1個体を別模式標本(allotype)に指定することがあります。ただし別模式標本はあくまでも参考であって、分類の基準にはなりません。
これらの模式標本は博物館や大学など公的機関の公式標本として登録されることが推奨されていて、個人コレクションの一部として保管することは好ましくありません。とにかく学術的に重要な標本ですから、保管を託された機関はそれを安全かつ確実に恒久的に保管しなければなりません。他方、学術の発展のために容易に研究に利用できるように他の研究者に対して便宜も図るべきです。
学名の変更
学名は国際命名規約の先取権の原則によってその安定性が守られているので、変わることはあり得ないと思いきや、実際には変更されることが多々あります。しかしそれはいずれもしかるべき正当な理由によるわけで、主に以下のような場合です。
1. ある学名が適用されている種が、実はその学名の種とは異なることが判明した場合(種の誤同定)
例えば、リンネの時代には専らヨーロッパ産の標本を基準にして新種記載が行なわれましたが、のちの研究者がそれ以外の地域の生物を同定(種名の査定)するのに既往の学名を当てはめるということがよくありました。しかしのちに模式標本等をよく調べてみたら実はヨーロッパ産とは別の種であったということもあります。このような場合には学名を誤同定されていた種は新種となるケースが多いですが、既にいくつか別の学名で発表されていた場合にはその中で最も古いものが適用されます。
2. 現在通用している学名が発表される前に、同じ種が別の学名で発表されていることが判明した場合(同物異名)
これもよくあるケースで、マイナーな雑誌に既に発表されていた学名が見逃されていたなどということがあります。この場合には先取権の原則によって最も古い学名が有効名となり、現在の学名がいくら広く普及していたとしてもそれは使用できなくなります。
ただし、最も古い学名であってもその存在を忘れ去られてしまって最近50年間に全く印刷物に用いられていないものは遺失名として破棄することができ、よく通用している新しい学名を有効名としてもよいということになっています(植物、細菌ではこの例外規定はない)。
3. あるタクソン(種名、科名など)の学名が既に別のタクソンの有効な学名として使われていることが判明した場合(異物同名)
この場合は発表されたのが古い方のタクソンの名称が有効で、新しいタクソンに対しては別の新たな学名を付けなければなりません。
また、2のケースと複合しますが、タクソンAの最古参の学名がタクソンBの異物同名であり、その学名がタクソンBの方に先取権がある場合、タクソンAの最古参の学名とは認められず、その次に古い学名がタクソンAの有効な学名となります。
4. 従来別の種と思われていたいくつかの種が実は同一種であることが判明した場合
この場合は、別々に付けられた学名のうちで最も古いものが有効名として残され、他の学名はすべて異名として破棄されます。
5. 従来同一種と思われていたものが実はいくつかの種が混合したものであることが判明した場合
これは4と逆のケースですが、この場合には模式標本が非常に重要になります。模式標本と同じ種に現在の学名を当て、その他の種にはそれぞれ新たな学名を与えることになります。
6. 属名と種小名の組み合わせによる変更
これもよくあることで、属が変更されるのは以下のような理由によります。
① その属名が何らかの理由(異物同名、同物異名など)により無効とされ属の学名が変更された場合。
② 研究の結果、その種の属する属が間違っていたことが判明した場合。
③ その属がいくつかの属に分割された場合。
④ いくつかの属が併合された場合。
リンネの時代には全般に大まかな分類で属の数も多くありませんでしたが、その後分類の細分化が進み、多くの新しい属が作られたことによる属名の変更が最も多いケースと思われます。
前述のように、属の変更により属名と種小名の性の不一致が生じた場合には、命名規約の規定により属名と一致させるために種小名の語尾を変えなければなりません(種小名が名詞の場合には適用しない)。
別属で種小名が同じ種が、分類の見直しによって同じ属に入れらる場合、二次的に異物同名が生じますが、この場合は記載が新しい方の種小名を変更しなければなりません。ただし、そのときに破棄された学名は未来永劫無効というわけではなく、将来の新たな分類見直しによってまた別属に分けられた場合には元の学名が再び復活することになります。
7. 命名規約の規定による強制変更
前述のように、一旦有効名となった学名は、たとえそれが綴り間違いや差別的な意味の語であっても変更することはできません。
ただし例外があって、原公表そのものの中に書写者や印刷者などによる不慮の過誤(inadvertent error)がある明白な証拠がある場合には訂正されます(例えば新しい種小名を提唱したときにその著者がその種を Linnaeus に因んで命名すると述べたにもかかわらず、その学名が ninnaei と公表されたならば、それは linnaei と訂正すべき)。不正な換字、不正なラテン語化、不適切な結合母音の使用などは不慮の過誤とは見なしませんから、この不慮の過誤のケースの適用は非常に厳密です。
また、科グループの学名において、各分類階級ごとに決められた語尾を用いていなかったり、語幹の形が不正である場合も正しい形式に訂正されます。属名の変更により種小名の語尾が変更されることがあるのも、何度も繰り返した通りです固有名詞に由来する学名の作り方
人名に由来するもの
属名の場合
人物に献名した学名を作る場合、属名の場合は人名に“~a”、“~ea”、“~ia”、“~ella”(以上女性形)、“~ius”(男性形)などの語尾を付けて作ります。植物と細菌では人名由来の属名の性は必ず女性にすると命名規約で決められていますが、動物では性は自由です。日本人に献名された属名は以下のようなものがあります。
例:Makinoa(マキノゴケ属)← 牧野富太郎から、Sasakia(オオムラサキ属)← 佐々木忠次郎から、Habea(イナザワハベガイ属)← 波部忠重から、Valenciennea(サザナミハゼ属)← Valenciennesから、Poinsettia(ポインセチア属)← Poinsettから、Dahlia(ダリア属)← Dahlから
種小名の場合
種小名に人名を用いる場合、形容詞化するか、ラテン語の文法規則に従って“~の”という意味の属格(所有格)にすることが命名規約で定められています。人名そのままの綴りを用いるのは神話(ギリシャとかローマ)上の名前か著名な古代人の場合に限られ、現代人名の場合は前述のような変化を加えます。ですから例えば Lateolabrax yokogawa のような用法は好ましくありませんが、しかしこれを文字の任意組み合わせと見なせば命名法上の不適格名とはなりません。
まず人名を形容詞化する場合、人名そのままの語幹の後に“~anus”または“~ianus”という語尾を付けます。形容詞ですから属名の性に対応して男性形では“~(i)anus”、女性形では“~(i)ana”、中性形では“~(i)anum”という語尾変化をします。
例:esakianus(江崎氏の)、sieboldianus(Siebold氏の)、brookiana(Brook氏の)
次に、人名を属格化するには、現代人の場合は語幹は人名そのままで、男性の場合は“~i”、女性の場合は“~ae”(ただし語幹が“~a”で終わる場合は“~e”)、男性複数または女性を含む場合は“~orum”、女性複数の場合は“~arum”という語尾を付けます。男性一人に献名される場合が多いので、“~i”の語尾が最も多いです(例えば前述の temmincki や schlegeli など)。
欧米人の場合は人名をラテン語化してから属格化することもあり、例えば Margaret はラテン語化すると Margarita または Margaretha となり、その属格は margaritae または margarethae となります。そのまま属格にするかラテン語化してから属格にするかは命名者の裁量に任されていますが、例えばおなじみのシーボルト(Siebold)の名前をそのまま属格化すれば sieboldi ですが、ラテン語化して Sieboldius としてから属格化すれば sieboldii となります。このどちらも容認される形式で、実際に両方の綴りの種小名が存在しますから、種によって綴りを混同しないように注意が必要です。ちなみに前述の Margaret の場合は、そのまま属格にした margaretae でも可です。
蛇足ですが、仮に井伊さんという男性に種小名を献名する場合、ラテン語化して Iiius としてから属格にすると iiii となりますが、果たして古今東西このような学名が存在するものかどうか・・・
人に学名を献名する場合、その生物を採集したり研究したりして直接関係がある場合にはその人名の属格を用い、単に敬意を表する場合には形容詞とする習慣ですが、厳密には守られていないようです。
地名に由来するもの
属名の場合
地名に因む属名を作る場合は、人名を属名にする場合と同様の語尾を用いますが、地名の綴りそのままの属名もあります。そもそも属名は名詞なので固有名詞をそのまま用いても支障がないのでしょう。
例:Nipponia(トキ属)← 日本から、Taiwania(タイワンスギ属)← 台湾から、 Chosenia(ケショウヤナギ属)← 朝鮮から、Niphon(アラ属)← 日本から、Alabama(アメリカ産蛾の属名)← アラバマから
種小名の場合
地名を種小名に用いる場合、一般に国名や広域の地名には“~icus”を語尾に用い、その他の地名には“~ensis”または“~iensis”を用いて形容詞化します。“~icus”は基本的な変化をする形容詞語尾で、男性形では“~icus”、女性形では“~ica”、中性形では“~icum”となります。“~ensis”の場合は、男性形および女性形が“~ensis”、中性形が“~ense”という変化をします。また、人名を形容詞化するときに用いる“~(i)anus”が使われることもあります。
例:anglicus(イングランドの)、indica(インドの)、pacificus(太平洋の)、chinensis(中国の)、nipponense(日本の)、brasiliensis(ブラジルの)、americanus(アメリカの)、africana(アフリカの)、romanus(ローマの)
地名が属格化されるケースは形容詞化に比べると多くはありませんが、人名の場合と同じ語尾変化になります。ラテン語では地名の名詞にも性がありますから、それに従って男性の場合は“~i”、女性の場合は“~ae”(語幹が“~a”で終わる場合は“~e”)、男性複数の場合は“~orum”、女性複数の場合は“~arum”という語尾を付けます。地名で複数形になるのは、例えば諸島のような場合です。
例:aegypti(エジプトの)、yokohamae(横浜の)、seychellarum(セイシェル諸島の)、philippinarum(フィリピンの)学名の意味と由来
多くの場合、学名はラテン語またはギリシャ語の単語あるいは複合語に由来しますから本来の意味を持ちます。学名を単に文字列として見るのではなく、例えば種ごとに意味がわかればまた認識も変わってくるものです。そこで以下にいくつか紹介したいと思います。
マダイ Pagrus major
属名はギリシャ語でタイの古名。種小名はラテン語で“大きい”という意味の形容詞magnusの比較級(長崎地方におけるマダイの地方名“マジャー”に由来するという説もある)。
オオクチバス Micropterus salmoides
属名はギリシャ語の複合語で、micro が“小さい”、 pterus が“鰭(原意は翼、翅)”という意味で、原記載をしたときに標本の鰭が欠損していて小さく見えたことによるらしいです。種小名はラテン語で“サケのような”という意味(~iodesは“~の形をした”という意味の形容詞を作るギリシャ語の語尾をラテン語化したもの)。
コチ Platycephalus indicus
属名はギリシャ語の複合語で、platy が“平たい”、cephalus が“頭”という意味。種小名はラテン語で“インドの”という意味の形容詞の男性形。
ホウボウ Chelidonichthys spinosus
属名はギリシャ語の複合語で、chelidon が“燕”、ichthys が“魚”という意味で、大きく胸鰭を広げた様子がツバメのように見えることに因むと思われます。種小名はラテン語で“棘のある”という意味の形容詞の男性形。
ニホンザル Macaca fuscata
属名の Macaca はサルを意味するポルトガル語起源のフランス語 macaque をラテン語化したもの(真っ赤っかという意味ではない)。種小名はラテン語で“黒ずんだ”という意味の形容詞の女性形。
コウノトリ Ciconia ciconia
ciconia はコウノトリのラテン名。属名、種小名に同じ単語が繰り返されていますが、これを反復学名(tautonym)といいます。反復学名は動物ではよくみられますが(特に鳥類に多い)、植物と細菌の命名規約ではこれは禁止されています。
カイコガ Bombryx mori
属名、種小名ともラテン語で、bombryx が“蚕”、mori は“桑”という意味の名詞 morus を属格にしたものです。
ヒトノミ Pulex irritans
属名はラテン語で“蚤”という意味。種小名もラテン語で、“刺激する”という意味の分詞形容詞。
オオミジンコ Daphnia magna
属名はギリシャ神話の Daphne に因みます。種小名はラテン語で“大きい”という意味の形容詞 magnus の女性形。
トウモロコシ Zea mays
属名はギリシャ語で、小麦の一種の古名。種小名は名詞で、トウモロコシの南米名。
フリージア Freesia refracta
属名はドイツ人医師の F. H. T. Freese(フレーゼ)に献名されたもので、英語の普通名詞としての読み方は“フリージア”ですが、固有名詞に由する学名なので原音に従って“フレージア”と読むのが学名としては正しいです。種小名はラテン語で“反曲した”という意味の形容詞の女性形。
クロマツ Pinus thunbergii
属名はラテン語で“松”の意味。種小名はスウェーデンの植物学者 C. P. Thunberg に因みますが、この場合は Thunbergius とラテン語化してから属格になっています。
モモ Prunus persica
属名はラテン語で“スモモ”の意味。種小名はラテン語の Persia(ペルシャ)を形容詞化したものの女性形。
また、日本産の生物には和名に由来する学名もかなりあります。以下にいくつか例を示します。和名が種小名に使われる場合は名詞としてそのままの形で学名になるようです。 特に、“j”で半母音の“y”の発音を表音していることが注目されますが、これはさきに解説したラテン語の正しい表音法によるものであることはおわかりでしょう。
Zacco(オイカワ属)←雑魚 に由来、Takifugu(トラフグ属)、Nibea(ニベ属)、Anago(ゴテンアナゴ属)、Kareius(イシガレイ属)、Sacura(サクラダイ属) Onigocia(オニゴチ属)、Katsuwonus(カツオ属)、akajei(アカエイの種小名)、tobijei(トビエイの種小名)、sajori(サヨリの種小名)、matsutake(マツタケの種小名)、nameko(ナメコの種小名)
このページの解説には以下の文献を参考にしました。学名についてさらに詳しく理解したい方は実際に読んでみて下さい。特に江崎悌三氏の解説はわかりやすくて推奨です。また、平嶋義宏氏のふたつの著書も学名について実例で数多く説明してあり、非常に参考になります。
- 秋元信一.1992.種とは何か.講座 進化⑦(柴谷篤弘・長野 敬・養老孟司 編),東京大学出版会,東京,pp. 79–124.
- 動物命名法国際審議会.2000.国際動物命名規約 第4版 日本語版.日本動物分類学関連学会連合,札幌,xviii+133 pp.
- 江崎悌三.1965.動物の学名.新日本動物圖鑑〔下〕(内田 亨監修),北隆館,東京,pp. 703–716.
- 平嶋義宏.1989.学名の話.九州大学出版会,福岡,380 pp.
- 平嶋義宏.1994.生物学命名法辞典.平凡社,東京,xv+493 pp.
- 池田清彦.1992.分類という思想.新潮社,東京,228 pp.
- 河底尚吾.1992.ラテン語入門.泰流社,東京,251 pp.
- 風間喜代三.1998.ラテン語とギリシャ語.三省堂,東京,214 pp.
- 馬渡峻輔.1994.動物分類学の論理.東京大学出版会,東京,viii+233 pp.
- 佐々治寛之.1989.動物分類学入門.UP BIOLOGY 74,東京大学出版会,東京,vi+124 pp.
- 高野秀昭.1980.動物と植物のなまえ.さかな(東水研業績C集),(24):1–7.
- 田中秀央 編.1966.羅和辞典.改訂新版,研究社,東京,xii+729 pp.
- 渡辺千尚.1992.国際動物命名規約提要.文一総合出版,東京,133 pp.
- 山口隆男.2001.シーボルト『ファウナ・ヤポニカ・魚類編』の成立.2001年度日本魚類学会年会講演要旨,82–85.
(文責 横川浩治)